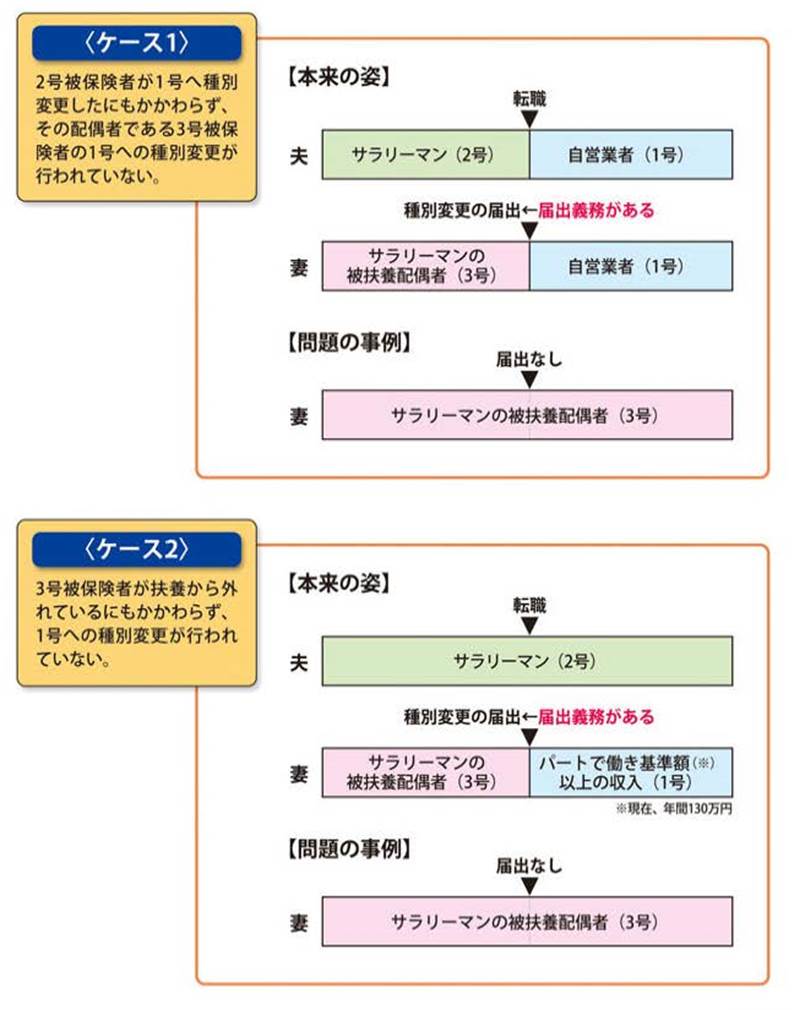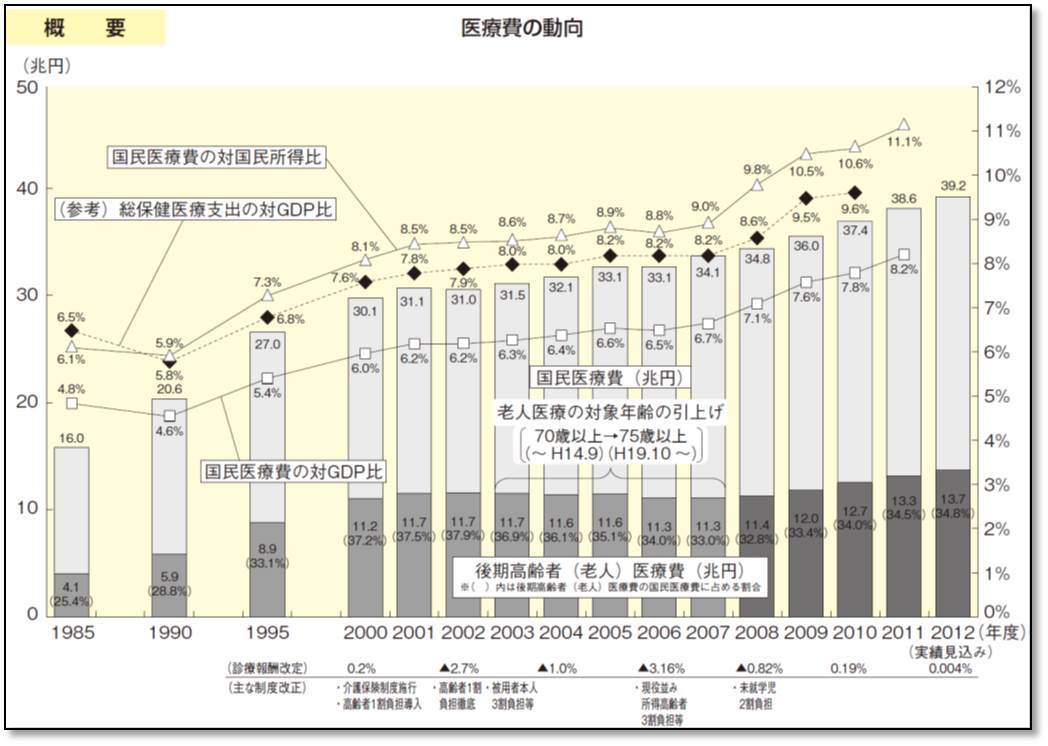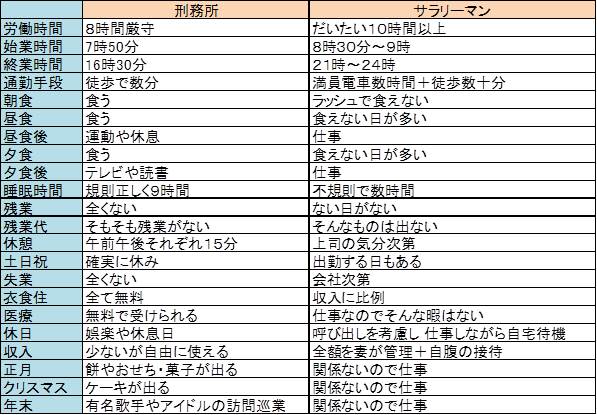厚生労働省は2016年4月から社員に年5日分の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける方針だ。19年4月からは中小企業の残業代も引き上げる。時間ではなく成果に対して賃金を払う制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)も、対象が広がりすぎないよう年収基準に歯止めを設ける。働き過ぎを防ぎながら規制を緩める「働き方改革」を促す。
6日をめどに開く労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に、報告書の最終案として示す。政府は今通常国会に労働基準法の改正案を出し、16年4月に施行する。
年休は6年半以上働けば年20日分もらえるようになるが、日本では実際に取った取得率が50%弱にとどまる。管理職を含むすべての正社員に年5日分の有休を取らせることを企業の法的義務にする。社員から有給取得を申し出る今の仕組みは職場への配慮で休みにくい。欧州諸国は事実上の消化義務を企業に課しており取得率が100%近い。日本も同じような仕組みを入れる必要があると判断した。
労政審に参加する労働組合の代表は過労を減らすため、年8日の義務付けを訴えていた。経営者代表は企業の負担が増えるとして3日分を主張しており、調整して5日になった。社員が自ら2日の有休を取れば、企業の義務は残りの3日分にする。すでに有休消化に取り組んでいる企業の負担が増えないようにする。
対象は年10日以上の有休をもらえる人に絞る方向だ。フルタイムで働く人は全員だが、パート社員は週4日、3年半以上働く人などに限られる。働く時間が短いパート社員はもともとの有休の日数が少ないうえ、過労になるリスクが小さいと判断した。
中小企業の残業代も引き上げる。月60時間を超える残業には通常の50%増しの賃金を払う。現在の25%増しから大企業と同じ水準に上げ、中小の経営者に過労対策に取り組んでもらう。16年4月の施行を目指していたが、残業が多いトラック運送業界が反対。施行時期をずらすことにした。※2015/2/4 日本経済新聞
———————————————————————-
<海外の反応>
http://www.japantoday.com/category/business/view/japan-eyes-compulsory-5-days-paid-holiday-a-year
◎5 days? How generous.People need more time off to recharge and be more productive in work and in life.Feeling tired all the time is a major problem for workers in Japan.
5日ですって? なんて寛大なんでしょう。人は充電し仕事や人生でより生産的であるためには、もっと多くの休みを必要とします。常に疲れていると感じることは、日本の労働者にとって大きな問題です。
◎And companies will fill out the false paper work “proving” that it has been taken.
そして会社は、それが取られたことを「証明する」偽りの事務書類を記入します。
◎Ooooo, five whole days! We’re being spoilt. This is bollocks.
おー、全部で5日!私たちは、甘やかされて育ったものだ。これはばかげている。
◎”5 days… FIVE???? European workers in civilised countries will start crying reading this.”
“5日… 5???? 文化的な国のヨーロッパの労働者は、涙なしにこれは読めないな。
◎Being a Gaijin working for Japanese company, its a nightmare to take 5 days continuous holiday.
日本企業で働いている外人です、その5日の連続休日をとる悪夢。
◎The problem here is in corporate culture it is a perfect storm of inefficency.
ここでの問題は、問題が複雑に絡み合って、それが効力の無いものとなる、企業文化である。
◎Full-time Japanese workers should get 10 mandatory days-off in addition to public holidays. It’s a shame they have to squeeze overseas trip into 5 days like most do now.
フルタイムの日本の労働者は、祝日に加えて10日の強制的休日を取得する必要があります。ほとんどが今でも行っているように、彼らが海外旅行を5日の中に押し込まなければならないのは残念です。
◎People here spend long hours at work, but most don’t spend long hours working. The amount of productivity is absurdly low.
ここの人々は仕事で長い時間を過ごしますが、ほとんどは働くことに長時間費やすことはありません。生産量は、とてつもなく低いです。
◎Welcome to the 20th century!
20世紀へようこそ!