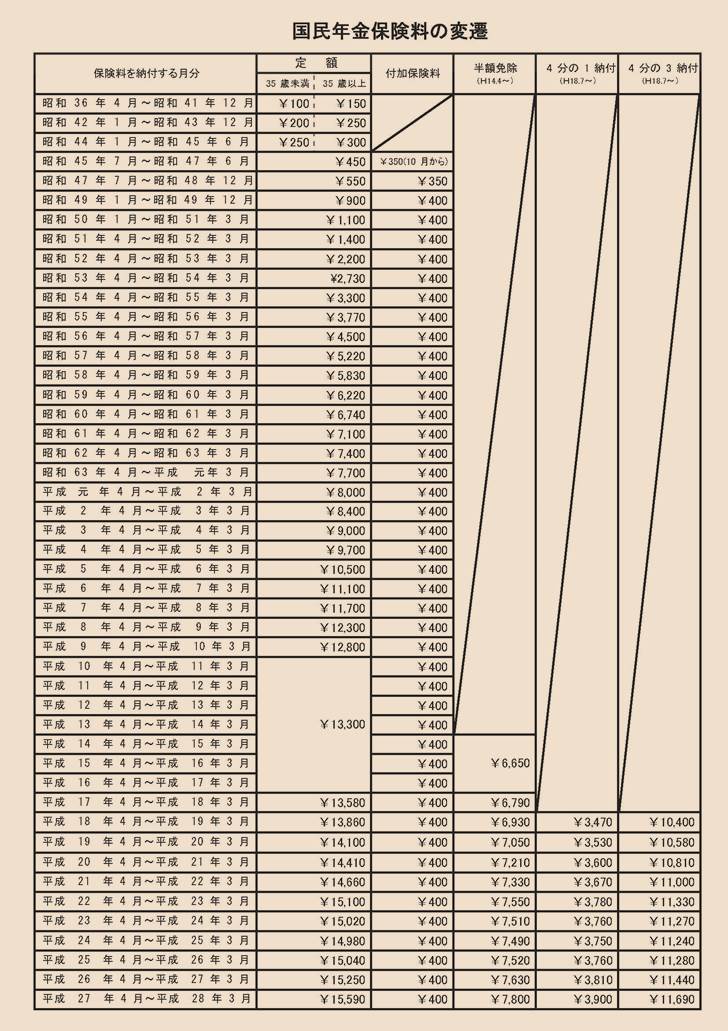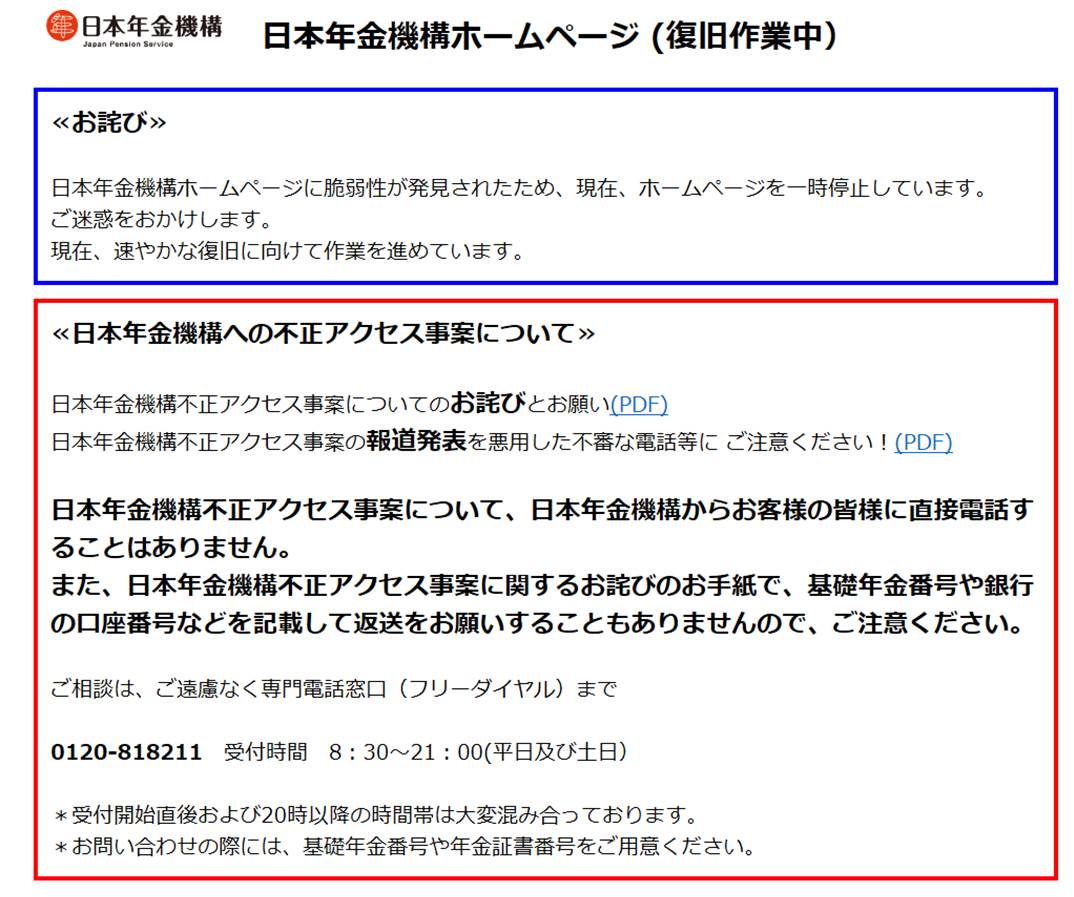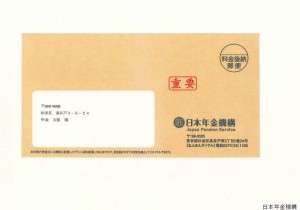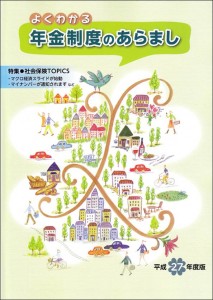【※2015/6/28 キャリコネニュースより】
米国では、原則として週40時間を超えて働くと「残業手当」が支払われることになっています。ただし年収2万3660ドル(1円=123円として291万円)以上の「管理職」は、この対象外となっています。
年収300万円足らずで「管理職」とみなされ、残業代が支払われないとは酷な話ですが、この抜け穴がいかに労働者の虐待につながっているか、経済特派員のポール・ソルマン氏が6月18日付のPBSニュースアワーでレポートしています。
<オバマ政権が支給対象者を増加へ>
クウェートからアメリカンドリームを狙って移民したガッサン・マルゾク氏。ボストンのダンキンドーナツのマネジャーだった彼は長年にわたって週75~80時間働いていましたが、残業手当は1セントも受けとっていません。
週40時間でも、100時間でも同じ給料でした。彼の月給を労働時間で割ると、時給9~10ドル(同1197~1230円)と普通の労働者よりも低くなります。
現行の規則では週40時間を超えた労働については、時給の1.5倍が支給されなければなりません。しかしマルゾク氏の上司は、彼を「管理職」と見なしています。お客にコーヒーを注いだりトイレ掃除をしたりという実際の仕事内容は、時給労働者と変わらないのですが。
マルゾク氏の弁護士シャノン・リスリオダン氏は、被雇用者に「管理職」の肩書を付け、残業手当を支払わずに週40時間を超えて延々と働かせるやり方は、米国国内で頻繁に行われていると批判します。
米国で1975年に残業手当を受け取ることのできた労働者は、全体の60%以上。それが現在では10%にまで減っています。これについてオバマ政権は2015年7月中にも基準を見直し、残業手当を受けられる労働者を増やすと見られています。
仮にインフレ調整ベースで1975年と同じ水準にすると、管理職とみなす収入の下限は年収5万1000ドル(同627万円)。これによって残業手当を受けられる人の数は600万人以上増えることになります。
<経営側は労働条件の低下を目論む>
しかし雇用者側の全国小売店連盟は、そんなに多くの人に残業手当を払うことなどできないと主張します。たとえばホワイトキャッスル・システムズ社では、給料制で働く管理職400人について、社会保障の条件を切り下げるか、時給労働者に変えると言っています。
懸命に働いて管理職にたどり着いた人々の働く機会も、これで奪われることになります。キャリアアップ志向も抑えられてしまうでしょう。
仕事のために子どもの卒業式にも出られなかったマルゾク氏は、残業を断ればクビを切られかねなかった。学位のない自分には、行き場がなかったと言います。彼は今、ガソリンスタンドで時給の仕事をしています。ここにも残業手当はまだありません。
日本でも労働基準法の改正によって、年収1000万円以上の高度プロフェッショナルには残業代を支払わなくてもよくなる制度が導入されようとしているようですが、米国の状況が参考になるかもしれません。
———————————————————————————————
この記事の元動画を拝見しましたが、米国も日本とおんなじ悩みを持っているんだなあと思いました。 Are bosses cheating workers out of overtime?
米国で残業手当を受け取っている割合が、10%程度なのは驚きですが、残業手当を支払わなくて済む経営側としては、給与計算が楽だろうなあ(^^)。。。
日本でも一時期・・・
「名ばかり管理職で残業ゼロ」「年俸制導入で残業ゼロ」
がにぎわった時期があります。今でも場所によってはあることでしょう。
現在導入予定の「高度プロフェッショナル制度」は、対象者や収入要件もあり、あまり心配することなく、プラス面のほうが多いかもしれません。
しかしながら今回、先行するアメリカからのレポートは、資本主義社会において(というより人類にとって)「週40時間労働を維持することの大変さ」を表していると思います。
そういえば昔、私も入社以来残業しなかった日は1日も無かったのに、残業手当をもらったことが1日も無かった記憶が・・・