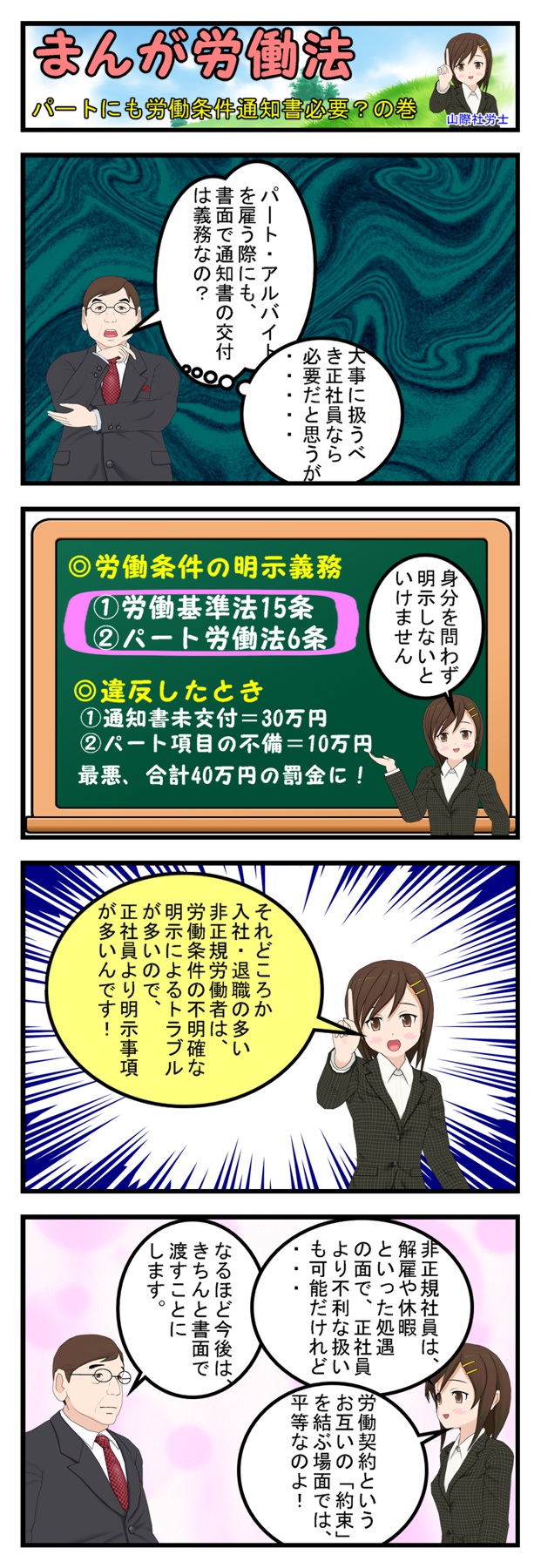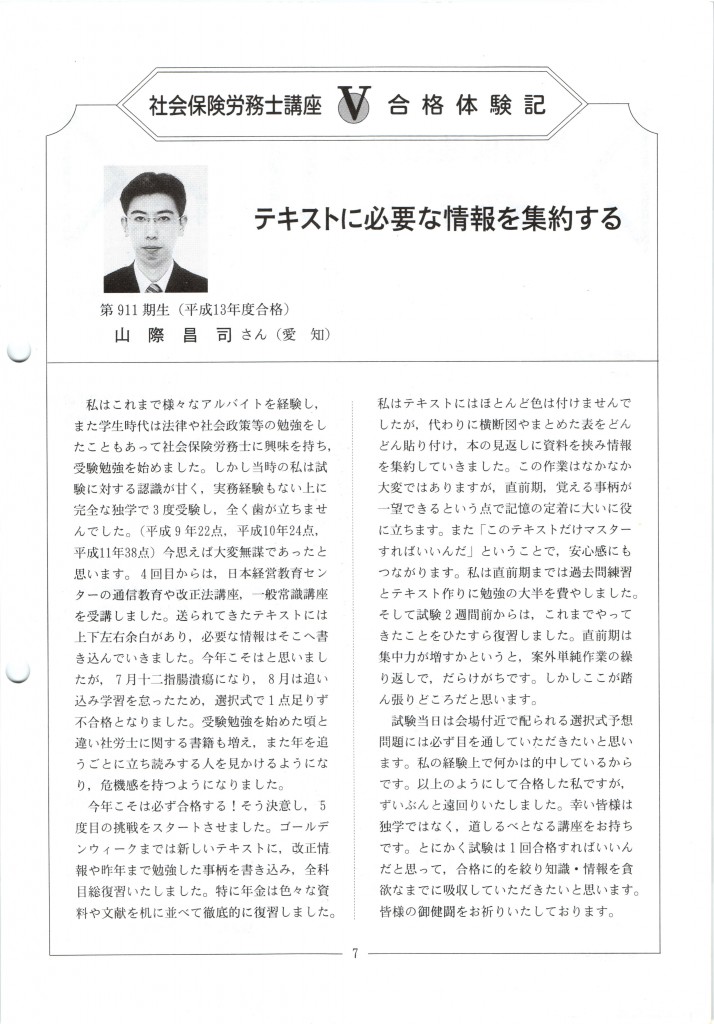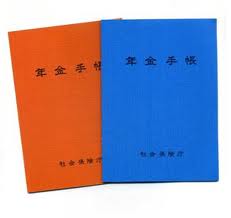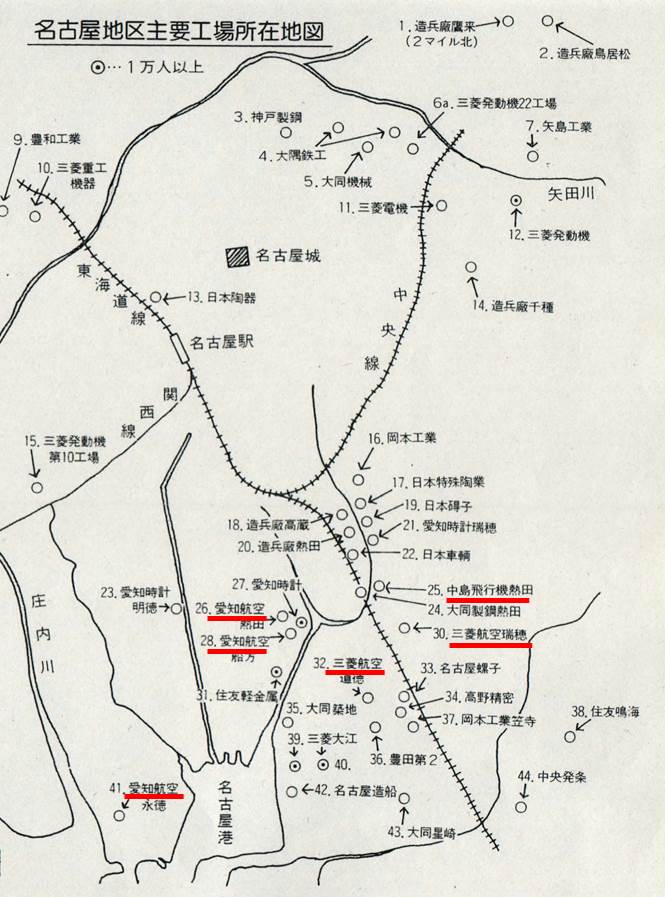8年ぶり位でしょうか?
今日は、美容院ではなく、床屋に行きました。
美容院と思って、たまたま入ったお店が床屋だったためです。
私は肌が弱いのか、店員がいつも通りの感覚で髭を剃ると、すぐスパッと切れてしまいます。
髭剃りされるのが、怖いんです(^^)
なので、次はまた美容院に戻ろうと思っています。
<理美容業界の社会保険加入>
最近は、理美容業界も、人手不足や社会情勢から、きちんと年金制度に加入している従業員さんは多くなりました。
しかし昔は、理美容業界といえば、厚生年金やら国民年金に加入されていない方が、非常に多かったです。
一時期、年金記録問題が多く発生しましたが、「理美容」「飲食」「大工」で勤務されていた方は、年金制度に加入していなかった方も多く、年金額が低額(又はもらえない)の状態です。
若い時代は、「将来生活保護を受ければいいから」と思っていても、生活保護は、資産やら親族など色々なことをさらけ出して、初めてもらえるので、案外大変です。
年金制度に加入することは、労使とも大変負担の大きいものですが、助成金・補助金、免除制度などあらゆる手段を活用しながら、極力、未納期間が少ない年金記録にしていただきたいと思っています。