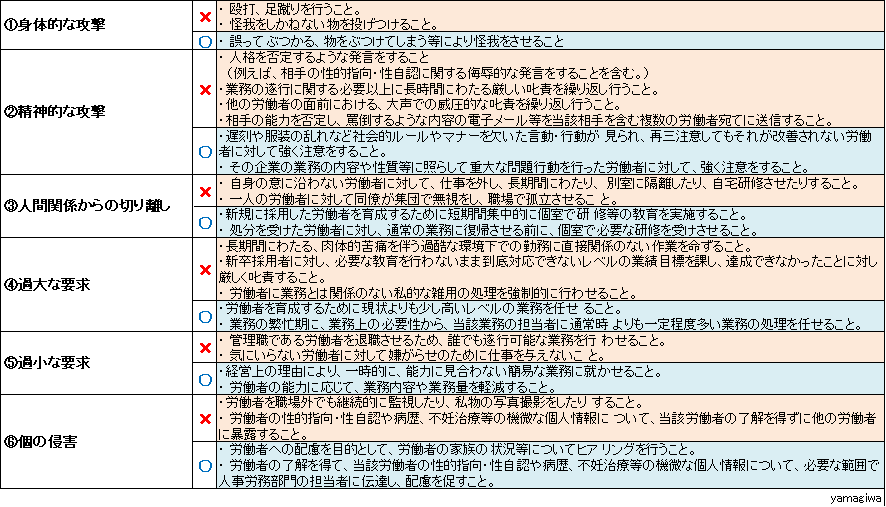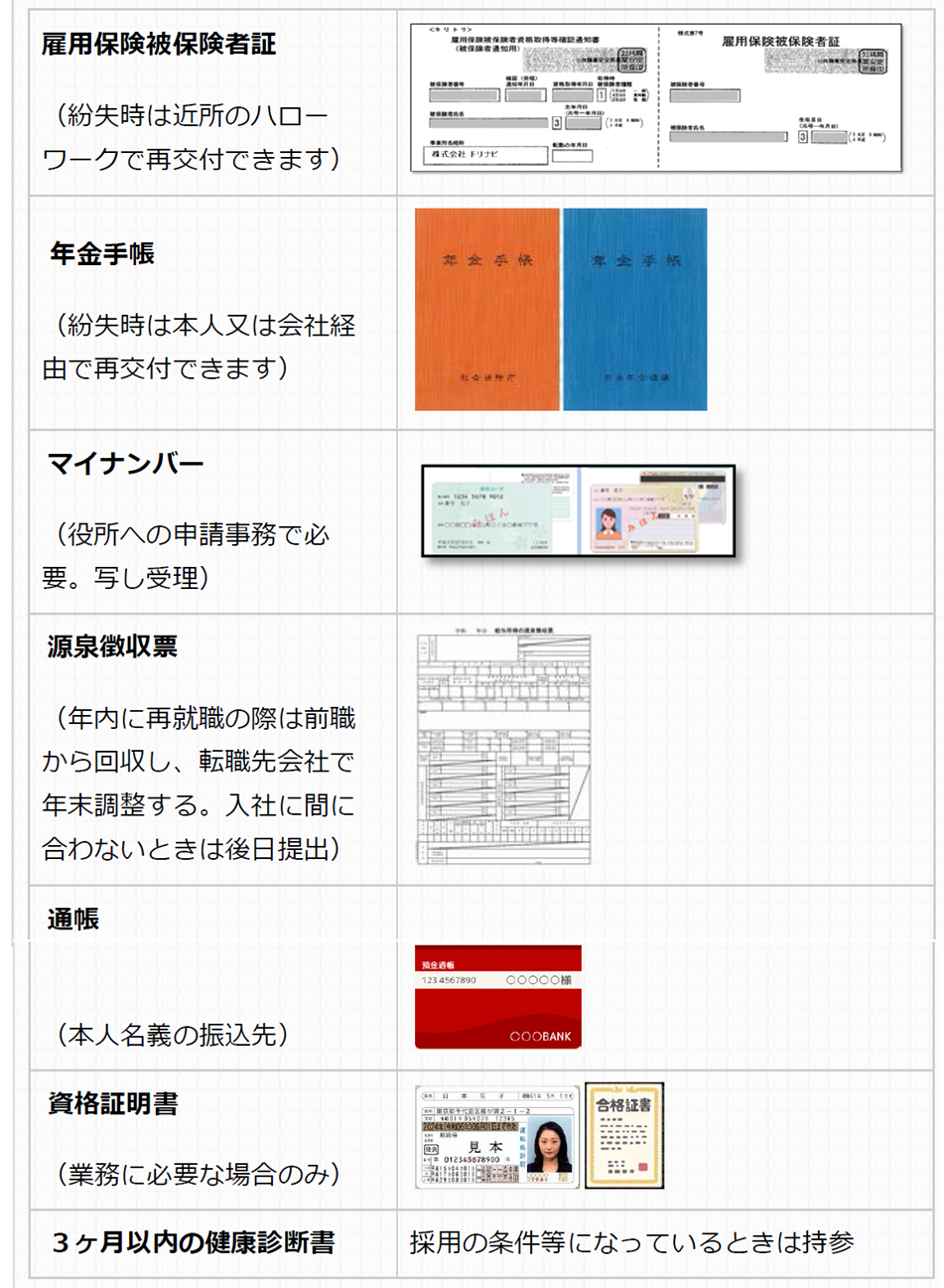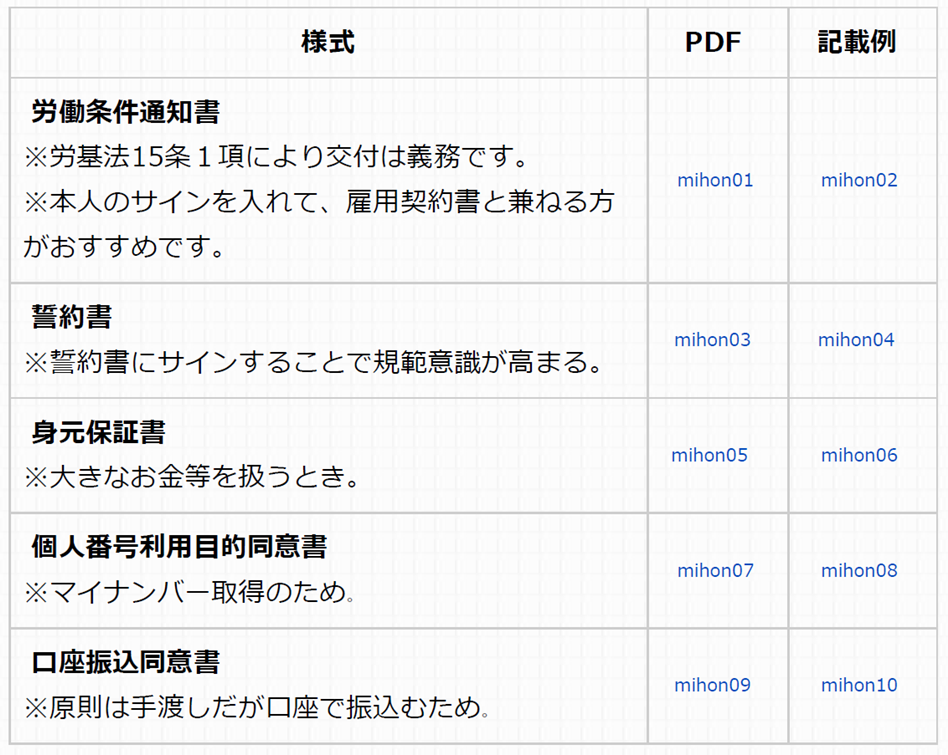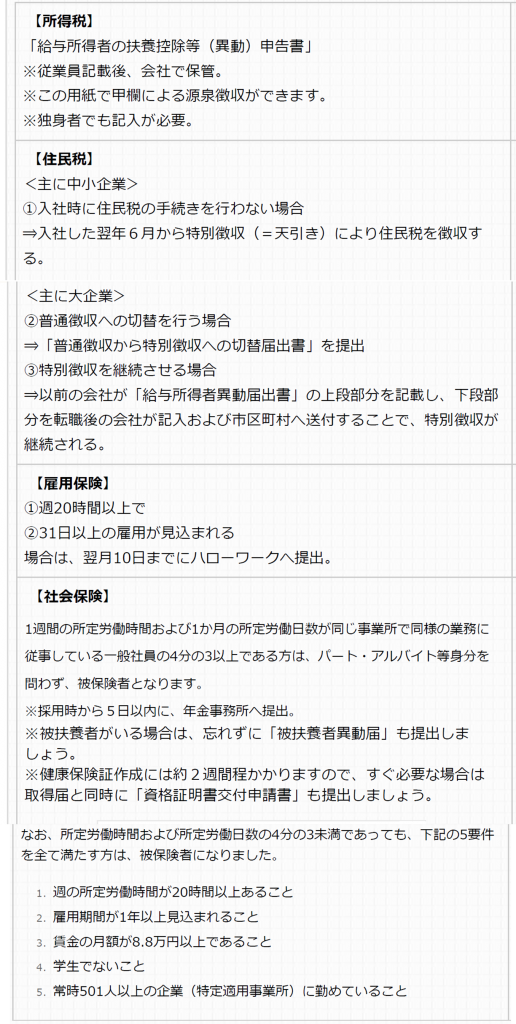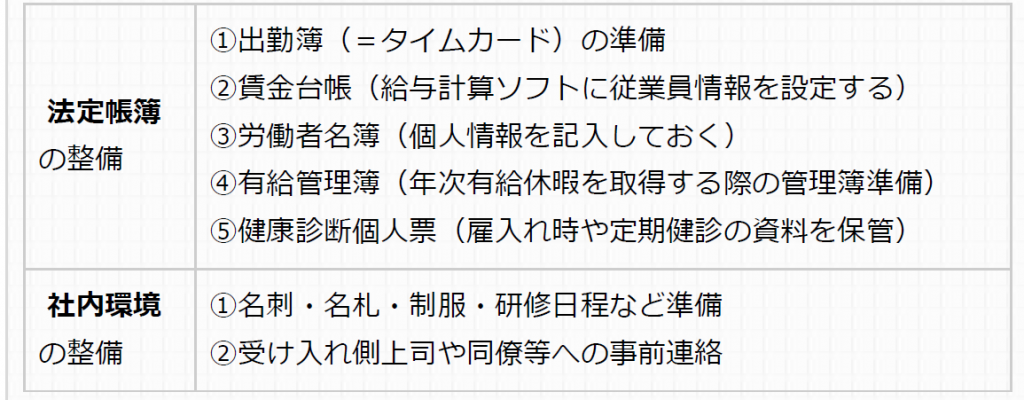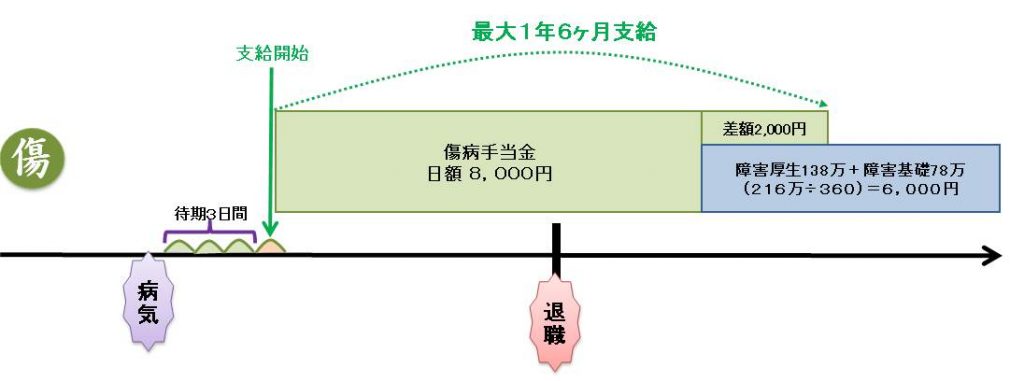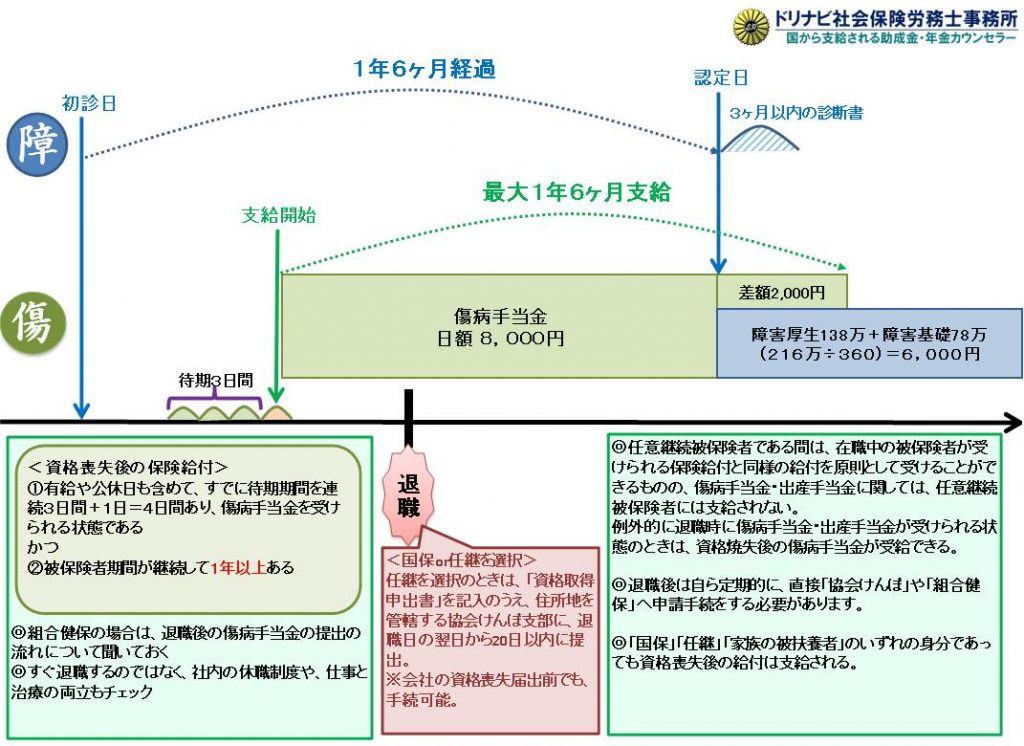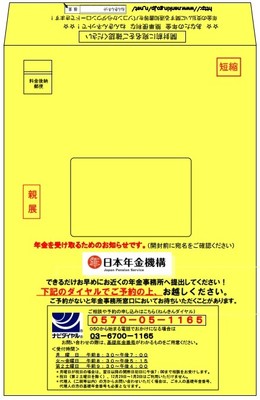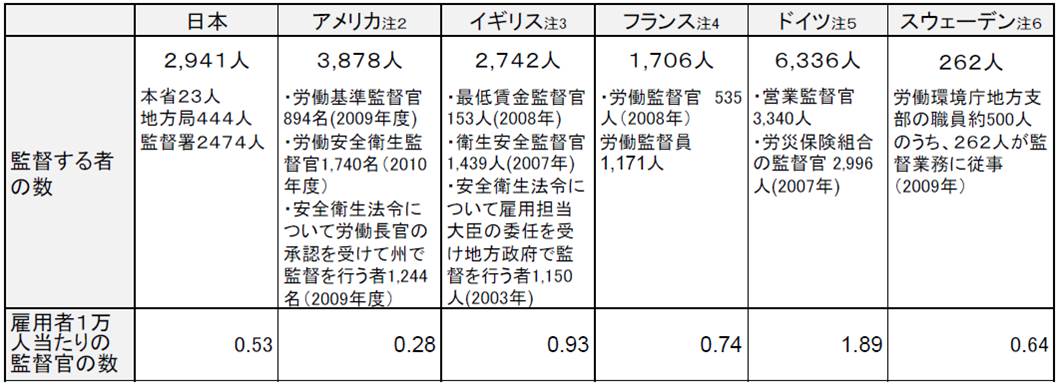令和元年5月29日成立、翌月6月5日公布された「改正労働施策総合推進法」。
令和元年5月29日成立、翌月6月5日公布された「改正労働施策総合推進法」。
今までパワハラという言葉はありましたが、今回、法律として初めてパワハラを定義しました。
(※条文は30条の2~という、なんともオマケ感がする場所にあります)
これにより国や企業、社長、役員はもちろん、この手の法律ではめずらしく・・・
上司や同僚を含んだ労働者に対しても、
パワハラについて知識を深めて、言動に注意するよう努めてください、としています。
[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”18″]「パワハラをしてはいけません」という法律は、まだありません。
あくまで今回は、防止対策を求める法律です。[/word_balloon]
さて、法律は出来ましたが、具体的にパワハラ防止の運用となりますと、企業等に求める指針が必要です。
その指針を制定する際の、さらに一歩手前の素案が、令和元年10月21日(月)、労働政策審議会で発表されたのです。
もちろん、まだ素案です。
ところが「パワハラじゃない例」を示したことで、逆に・・・
[word_balloon id=”5″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”18″]加害者の「弁解カタログ」として使われるんじゃない?[/word_balloon]
そういう懸念もありますので、素案の内容がそのまま指針にはならないのでは、といわれています。
例えば、「過小な要求」で、OK事例として、
・経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就 かせること。
とありますが、「パワハラしてま~す!」なんて言う人はいないので、「いやいや、経営上の理由っすよ!」という言い訳見本を提示することになるのでは?という懸念です。
さて、パワハラと呼ばれるかどうかは、すでにこの法律ができる前から、「6類型」に分類しています。
※今回の素案では、次のような例を挙げました。皆さん、いかがでしょうか?
[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”18″]パワハラ対策は、大企業は2020年4月1日からスタートですよ![/word_balloon]
[quads id=2]